受験シーズンがやってきました。
もう20年も前の出来事なのに、今もこの季節になると、あの時期のことをリアルな手触りで思い出してしまいます。
今進路を迷っている人とか、受験が未だ引っかかってる人に届けばいいな。
――――――――――
私は今でも、東大に落ちたことを、きちんと消化できていない。
ヒーターの熱がこもる教室で、窓の外の吹雪を眺めながら、黙々と自分と向き合った、あのたった半年を鮮やかに思い出す。
高校生の私は、東大に行きたいなと、うっすら思っていた。
東北の高校生だった私にとって、東大は全然身近な大学じゃなくて、ドラマとか漫画で出てくるなんかすごい大学。
東京の高校生からすると「ハーバード」くらいの遠さだったと思う。
東大に憧れた理由も「日本一だから」「すごいから」という、ふんわりした理由だった。
でも、憧れってそんなもんでしょ?
ただ、東大に入るために何かを努力していたわけではない。
自由を売りにした進学校に入った私は、
授業中に漫画を読み、MDであゆとB‘zを聴き、履き違えた自由を満喫していた。
当然、模試の成績もどんどん下がる。
高校入試の時点では、自分より下の成績だった子たちに、どんどん抜かされている意識はあった。
赤点をとったことを誇り、バカな自分に酔いしれていた。
「本当はやればできるし?」
「地頭はいいんだから」
そんな歪んだプライドで、自分を麻痺させる。
「このままじゃどこも受からないよ?」
高校3年生の春、担任との面談で言われたが、なぜか焦りはなかった。
当時の私は、人生なんて考えてもいなかった。
東大に対する憧れはあったけど、
現実は、このまま地元の国立大と地元の私立大を受けて、どこかに進学するんだろう。と頭の片隅では思っていた。
だって東大は、ドラマとか漫画の世界だから。
私が生きる現実の世界は、この東北の、地元の国立大をトップとしたヒエラルキーの中だから。
.
ある日、友達と占いに行った。友達が行きたがってた占いの付き添い。
魔女の家っていうタロット占いのお店だった。
蛍光灯がついた普通の会議室をパーテーションで区切っただけの部屋に、ちょっと拍子抜け。
蝋燭の灯りに、布で仕切られてる部屋を想像していた。これだったら隣の古着屋の方がよっぽど雰囲気がある。
占って欲しいテーマもなかったから、あたり触りのない「受験生なんんですけど、受験はどうなりますか?」ってノリで聞いた。
魔女は、ちょっとパサついた毛先に土気色の顔で気怠げに聞いてきた。
「受験ね、志望校は?」
「○○大学(地元の国立大)です」
手際よく切られるカードをドキドキしながら見つめる。
結果にドキドキするというより、初めて目の前で切られるタロットにドキドキしていた。
最後のカードを、思いのほか強く叩きつけるように開くと、魔女は言った。
「あなた、迷ってる?」
その一言を強烈に覚えている。
「え?なんでですか?」
「カードがそう言ってる。本当は別の大学を受けたいんじゃない?」
ど真ん中に斜めに置かれたカードは「月」。
迷いを表すタロットだ。
そのあとは何を聞いたか覚えていない。
ただ、迷っているかと問われたことに、自分でも驚くほど動揺しているのを感じた。
私、東大にいきたい。
思い浮かんだワードが自分の腹に落ちてくる感覚。
と、同時にその重さに覚悟が決まる。
あの日、私は初めて自分の願望と向き合ったのだ。
ただこの時は、この選択が、この先思ったよりずっと
私の人生で長く引きずる出来事になるとは思っていなかった。
翌日、私は母親に宣言した。
「私、東大を受ける」
当時の成績は最下位から数えて1桁。
高校3年生、夏休み直前のことだった。
――――――
あの頃の私は占いで人生を決めちゃったんですね。
というより、占いで言われたことで、自分の本音と向き合えた、っていうのが正しいのかもしれません。
自分の本当の願望と向き合うのが、今より下手だった。
あの一言がなければ、きっと私は東大を受けたいって気持ちにも気づかないで、今もふんわりとした“憧れ”だけを抱いていたのかなと思います。
それはそれで、後悔したんだろうなと。
この話は数話に分けて続けていこうと思ってます!
続きはこちら(※まだリンクないです)
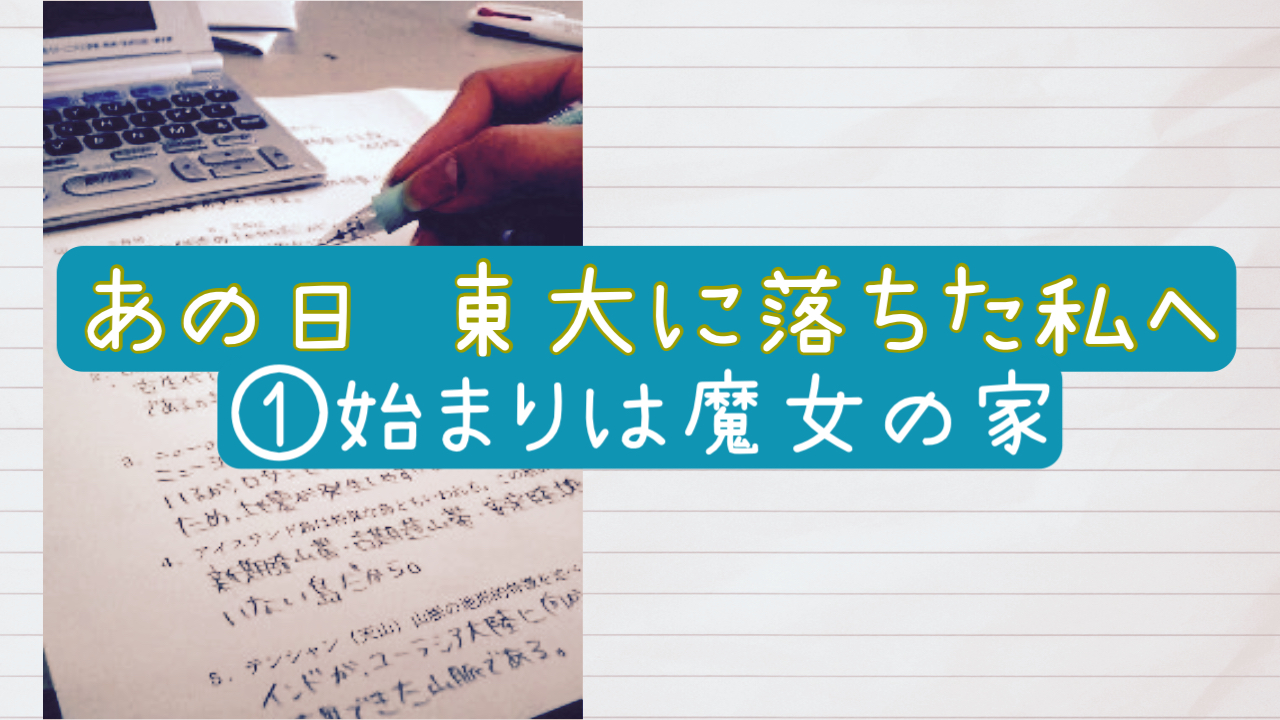


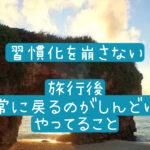
最近のコメント